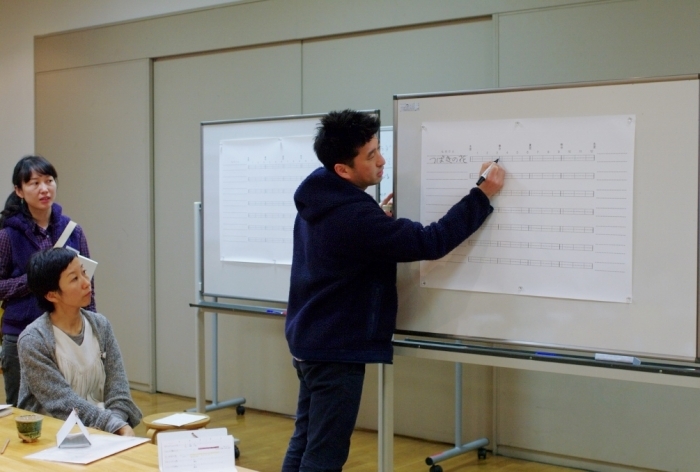4月ですね。新年度・新学期。日本では、新生活のスタートをきる月です。
生活工房でも、去る人あり、来る人あり。かくいう私も、部内での席替えがあり、ほんのちょっと移動しました。
桜が咲いたと思ったらもう散っていく。時は、ときに一瞬のうちに駆け抜けていきます。
生活工房では、「この星に生きる」をテーマに活動しているセセンシトカさんと共同で、「時をときはなつ」と題した企画をおこなっています。
カレンダーや時計の中に押し込まれてしまっている「時」の概念をときはなち、自分やほかの命の中に流れる時間、世界に流れる時間を見つめることを目的に、ワークショップと上映会を行っていく、というものです。
そのvol.2として、時のフィールドワークショップ「春の道ばたで、若菜摘む」を3月21日に、時のドキュメンタリー上映会「移動の時」を3月28日に開催しました。(vol.1はこちら)
*****
時のフィールドワークショップvol.2「春の道ばたで、若菜摘む」
開催日はちょうど、春分の日。
暖かい日も増えたけれどまだ冬物のコートをしまえない、そんな日に、春の芽吹きを探しに出かけました。
特別講師として、沖縄より花作家のかわしまよう子さんをお招きし、世田谷の中でも都会といわれている三軒茶屋の道ばたを歩きます。
国道246の下ににょきっと咲いていたノゲシ。団地の柵のふもとに咲く、ムラサキハナナや、ミミナグサ。
かわしまさんが親しげに草たちを紹介するので、そのひとつひとつが人格ならぬ草格を持っているように感じられます。
摘み取りを予定していた公園では、ツクシ、スギナ、ヨモギ、カラスノエンドウ、タネツケバナ、ノビルなど、たくさん採集することができました。
生活工房に戻って、早速調理開始!
ヨモギのおむすび、カラスノエンドウの天ぷら、タネツケバナの白和え、ツクシとスギナの炒めもの、ノビルのチヂミ(あ、のびるちぢみ…)など、たくさんのお料理が並びました。
かわしまさんは、都会こそ、こうした草について学び、感じ、ふれあえる企画が大切だといいます。
都会に暮らす私たちは、つい、「自然」と「都会」を対極のものと考えてしまいがちです。しかし、だからこそ、「自然」で起きていることに、無関心になっているのではないでしょうか。
都会の中にも、自然のリズムが息づき、道ばたには知らず知らず、雑草が生えてくる。一見コントロールされているような世界に、アウトオブコントロールなものが入ることは、逆に、私たちに命の力強さを知らせてくれます(ど根性大根のような・・・)。そして、都会の一部に自然があるわけではなく、やはり自然のリズムの中に都会が築かれているのだと、感じることもあるのではないでしょうか。
雑草料理を食べたあとは、セセンシトカの佐々木光さんの出番。「時のフィールドノート」を使って、今日見た・採った・食べた草花の「時」をふりかえります。
そして、ご参加の皆さんに、「私に時(春)を知らせてくれるもの」について、伺っていきました。
「春は沈丁花、秋は金木犀の香り」
「空のかすみ、うろこ雲、入道雲など、空にサインを感じる」
「冬は抜け毛が減る。守られている感じがする」
「夏は土と草の香りがする」
いっぽうで、「自分はカレンダーやスーパーで季節を知っていたということに気が付いた」という方もいらっしゃいました。
しかし、その方は、翌週の上映会にも来てくださり、「あれから雑草が慕わしくて慕わしくて」とこぼれる笑顔でおっしゃいました。来年の春の訪れは、カレンダーやスーパーではなく、きっと道ばたで知ることになるのでしょうね。
*****
時のドキュメンタリー上映会vol.2「移動の時」
先に書きましたように、日本では4月が新年度の始まりで、そのために入社・入学・異動などで、転居される方も多いと思います。しかし、世界の人びとや動物たちは、「明日から4月だから」移動するわけではありません。
世界の人びとは、どのような理由とタイミングで、「移動」をするのでしょうか?その問いに答える映像を多数上映しました。
○「ブッシュからブッシュへ 遊牧ソマリのキャンプの移動」(ラクダに家の骨組みと家財道具を載せて移動)
○「ザンビアのクオンボカ ロジ族の大移動」(川の氾濫のタイミングで王宮ごと船で引っ越す)
○「キルギス族の生活」(季節により、山の高地と低地を行き来する)
○「奥会津の木地師」(木で椀などを作りながら数十年、山から山へ移り住む)
○「サーミ人のテント」(トナカイとともに遊牧生活を送る)
○「驚異の大移動」(ヌーの大移動、森と海を行き来するカニ、4世代かけて数千キロ移動する蝶など)
この映像6作品に出てくる人びとも動物も、みな「生きる」ために移動しています。
でももしかしたらそれは、「生かす」ためなのかもしれません。
「移動の時」をテーマに、そんな企画者の思いを座談会としてまとめ、当日配布しました。
配布資料は、こちらよりダウンロードもできます→ときどき座談会
当日は、「奥会津の木地師」のカメラマン、伊藤硯男さんもご来場いただき、作品について少しお話しいただくという、うれしいサプライズもありました!
最後に、参加者の皆様のご感想を。
「地球の鼓動にもっと耳を心を感覚を傾けたいなと思いました。たくさんの気付きをいただきました」
「食・住・生を求めて移動していく大きな摂理を感じました」
「生きものの大移動を見て、種として生き延びるために、資源を絶やさないための行動なのかなと思いました。では、人間はどうしたらいいのかな?」
「大自然の中、人も動物もたくましく、野生の生きものたちの感覚・本能、引き継がれた人間の智恵。感動・感激でした。今自分たちが生きている文明の行く末を想い地球を案じてしまいます」
「地球はなんて面白いところだろう」
次回、「時をときはなつvol.3」は、6月下旬―7月頭に予定しています。どうぞお楽しみに!!